生活習慣病とは
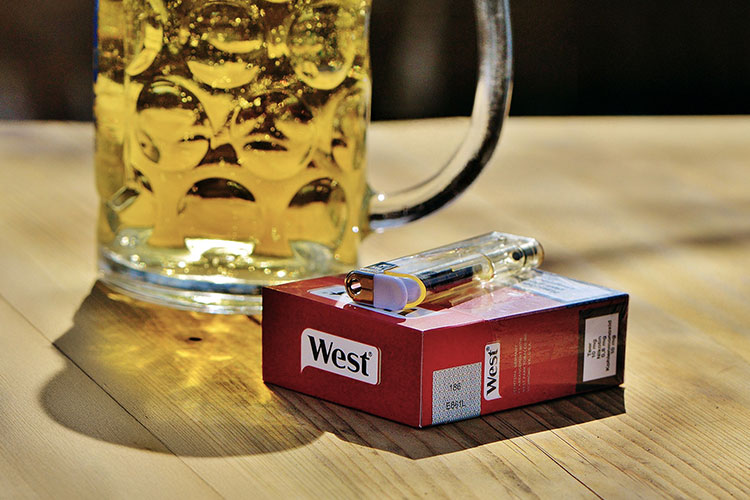
不摂生とされる日頃の生活習慣(偏食・過食、運動不足、喫煙、飲酒、ストレス等)が蓄積することで発症する病気を総称して生活習慣病といい、糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症などが含まれます。
これらの病気は、いずれも自覚症状がないまま病状を進行する特徴があります。そのため未治療のまま放置しやすく、この状況が続くと動脈硬化が進行します。それでも症状がないことが多く、その間も常に血管は損傷し続けています。やがて血管狭窄や血管閉塞が起き、気づいた時には、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、閉塞性動脈硬化症などの重篤な合併症を発症するということも少なくありません。
自覚症状がなくても定期的な健康診断を受けるようにしてください。その結果から生活習慣病に関係する数値(血圧、血糖値、コレステロール値 等)で、医師から数値の異常を指摘された場合は医療機関を速やかにご受診ください。早めに発症に気づく、あるいは生活習慣病予備群であることがわかれば、その時点で治療や予防に努めることができるので、合併症発症のリスクを減らすことができるようになります。また数値に異常がなくとも日頃の生活習慣を見直すことができれば、生活習慣病に罹患する可能性を遠ざけることにもつながります。
主な生活習慣病
高血圧はこちら
糖尿病
糖尿病とは
血液中に含まれるブドウ糖の濃度(血糖値)が基準とされる数値よりも慢性的に高い時に糖尿病と診断します。具体的な診断基準は以下の通りです。
- ①血糖値の数値:早朝空腹時血糖値が126mg/dL以上、もしくは75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値が200mg/dL以上、あるいは随時血糖値が200mg/dL以上
- ②HbA1cの数値:6.5%以上
※①と②がともに当てはまる場合は糖尿病と診断されます。①もしくは②のみ該当する場合は「糖尿病型」と判定され、もう一度検査を行います。再検査の結果も「糖尿病型」となれば糖尿病と診断されることになります。
糖尿病の種類
ブドウ糖は脳や体のエネルギー源であり、血液から細胞に取り込まれます。その際には膵臓から分泌されるインスリン(ホルモンの一種)の働きが欠かせないのですが、何らかの原因によってインスリンが作用不足を引き起こすことがあります。この状態になると、ブドウ糖は細胞に取り込まれずに血液中で増え続け、慢性的に血糖値は上昇したままとなります。これが糖尿病です。その種類には大きく2つあります。
ひとつは1型糖尿病です。これは主に自己免疫反応によって、インスリンを産生する膵臓のβ細胞が破壊されてしまうことでインスリンが分泌されなくなっている状態です。もうひとつのタイプは、2型糖尿病といわれ日本人の糖尿病罹患者の大部分がこちらになります。この場合、糖尿病になりやすい体質(遺伝的要因)であること、不摂生な生活習慣(過食、運動不足、喫煙、飲酒、ストレス 等)などが原因といわれています。2型では膵臓が疲弊しており、インスリンの分泌が不足している、あるいはインスリンの量は十分でも効きが悪い状態(インスリン抵抗性)となっています。
上記以外では糖尿病以外の病気に罹患、あるいは薬剤の影響等によって発症する糖尿病(その他の特定の機序、疾患によるもの)があります。さらに妊娠中の女性の胎盤から分泌されるホルモンで、インスリンが効きにくくなって高血糖状態になってしまう妊娠糖尿病というのもあります。
主な症状について
糖尿病は発症しても自覚症状が出にくい病気です。病状が進行すると、喉の異常な渇き、多尿・頻尿、全身の倦怠感、食欲があっても体重が減少するなどが見られるようになります。血糖値が上昇したままの状態が続くと、発生した活性酸素によって血管は損傷を受け血管障害がみられるようになります。とくに細小血管が多く集まる、網膜、腎臓、末梢神経で起きやすく、これらは糖尿病三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)と呼ばれています。また太い血管での動脈硬化が進行することで虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、脳血管障害(脳梗塞 等)などの発症リスクも高まるようになります。
治療について
1型糖尿病は、体内でインスリンが分泌されていない状態であり、体外からインスリンを補充するための治療が行われます(インスリン注射)。
一方で2型糖尿病はインスリンがある程度分泌されており、生活習慣の見直し(食事療法、運動療法)から始めていきます。食事療法では、適正なエネルギー摂取量を厳守する(食べ過ぎない)。さらに一日三食を規則正しくとる、栄養バランスのとれた食事に努めるといったことが大切です。
また適度に運動することは、インスリンの働きを改善させるので日常生活に取り入れるようにします。ただハードな量は必要としません。息がやや弾む程度の強度で、1回30分以上の有酸素運動(軽度なジョギング、ウォーキング 等)で効果がみられるようになりますが継続的に行うようにしてください。
生活習慣の改善だけでは血糖のコントロールが難しい場合や血糖値が最初から極めて高い場合は、併行して薬物療法も行います。糖尿病の状態によって、インスリン抵抗性を改善する薬(ビグアナイド薬、チアゾリジン薬)、インスリンの分泌を促進する薬(スルホニル尿素薬、DPP-4阻害薬、速効型インスリン分泌促進薬)、糖吸収・排泄を調整する薬(α-グルコシダーゼ阻害薬、SGLT2阻害薬)などが用いられます。それでも効果が乏しいときは注射薬(インスリン、GLP-1受容体作動薬)が選択されます。
脂質異常症
脂質異常症とは
血液中に含まれる脂質には、コレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸の4種類があります。そのうちLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が血液中で多いときや、HDL(善玉)コレステロールが少ない時に脂質異常症と診断されます。血液検査をすることで発症の有無がわかるようになりますが、具体的な診断基準については以下の表の通りです。主に3つのタイプに分けられます。
- 高LDLコレステロール血症
- LDLコレステロールが140mg/dL以上
- 高トリグリセライド血症
- トリグリセライド(中性脂肪)が150mg/dL以上
- 低HDLコレステロール血症
- HDLコレステロールが40mg/dL未満
数値が異常なら症状がなくても
ご受診ください
コレステロールは、細胞膜やホルモンを作る材料になります。また中性脂肪は糖質が不足している際には体のエネルギー源として使われ、皮下脂肪となって体温調節をするなど体にとって不可欠なものです。しかし余剰な脂質は血管内にLDLコレステロールが蓄積させ、動脈硬化の原因となります。脂質異常症は発症しても自覚症状が出ないので、放置し続けることもよくあります。その後、血管に狭窄や閉塞がみられることで、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、脳血管障害(脳梗塞 等)といった重篤な合併症が現れ、その際に脂質異常症に初めて気づいたという患者様も少なくありません。このような状況に陥らないためにも、定期的に健診を受け、脂質異常症に関する数値の異常を指摘されたら一度当院をご受診されるようにしてください。
発症の原因については、家族性高コレステロール血症など遺伝的要因のケースもあります。それ以外では、糖尿病や甲状腺機能低下症など別の病気の発症、肥満、お酒の飲み過ぎ、薬剤の影響(ステロイドの長期投与 等)などがあります。
治療について
治療としては食事療法・運動療法・薬物療法がありますが、過去に脳・心臓の血管に病気を発症したことがある方は、再発を予防(二次予防)することが特に重要なため食事療法や運動療法に加えて薬物療法の併用が必要です。それらの病気を発症していない方は、脂質異常症以外の生活習慣病(高血圧症や糖尿病)、喫煙などから将来の動脈硬化リスクを個別に判断し高リスクでない場合は、まずは生活習慣の改善から始めます。中でも食事療法は重要であり、肉の脂や動物性の脂(牛脂やバター、ラード等)よりも(青)魚の摂取が望ましいです。そのうえで、コレステロールを蓄積させにくくする食物繊維の豊富な食品(野菜、きのこ、海藻、果物、未精製穀類)や大豆製品を積極的に食事に取り入れていきます。調理方法も揚げ物は避け、焼いたり蒸したりする調理を中心とします。またお酒を控え、マーガリンやショートニングを用いた料理や糖分を多く含むお菓子も避けるようにし、伝統的な日本食(ただし減塩したもの)を意識した食事を心がけます。
体を動かすことは、トリグリセライド(中性脂肪)を減らし、HDL(善玉)コレステロールを増やす効果があるので、運動療法も取り入れます。中強度の運動(ややきつい程度)のウォーキングやジョギング、水泳、自転車等の有酸素運動が効果や安全面から適しており、1日30分以上の運動を週3回以上できれば毎日行うのが望ましいです。
生活習慣の見直しで目標となる数値を達成することが困難な場合や、生活習慣が改善できない場合は薬物療法も行います。この場合、スタチン系薬剤の内服(LDLコレステロールを下げる効果がある)が多いですが、医師が必要と判断すれば、フィブラート系製剤やEPA製剤(魚の油が原料となる)など別の治療薬が用いることもあります。
高尿酸血症(痛風)
高尿酸血症とは
血液中の尿酸の濃度(尿酸値)が高い時に高尿酸血症と診断します。
尿酸は水に溶けにくい性質があり、高尿酸血症の状態になると結晶化するようになります。この状態を尿酸塩といい、血液中に存在するようになって関節に溜まることがあります。これを異物と認識した白血球が排除しようと攻撃することで、患部が炎症を引き起こし、激痛に見舞われることがあります。これが痛風発作(一般的には痛風)です。発症後24時間が同発作のピークで1週間が経過する頃には治まりますが、痛風発作改善後に尿酸値を下げるための治療をしなければ再発するリスクが高いです。
高尿酸血症の状態であっても痛風発作がみられないこともあります。無症状の場合でも尿酸値が高い状態が続くと慢性腎臓病、尿路結石、痛風結節のほか動脈硬化を促進させることによる脳血管障害(脳梗塞 等)や虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症 等)などの合併症を発症するリスクが上昇します。
尿酸が増える原因
尿酸が増える原因には尿酸産生過剰型と尿酸排泄低下型、その両者の合わさった混合型があります。尿酸産生過剰型は尿酸が体内で必要以上に産生されることで尿酸が増加します。これは尿酸の元となるプリン体を多く含む食品(煮干し、レバー、カツオ、大正エビ 等)やアルコール(ビール)の過剰摂取をはじめ、先天的な代謝異常、白血病等の造血器疾患などが挙げられます。尿酸排泄低下型は尿酸が体外に排泄しにくいことで発症し、これは脱水症、利尿薬の使用等による薬剤の影響、腎機能の低下、尿崩症などによって引き起こされます。両者の合わさった混合型については肥満の方によく見られます。
治療について
血清尿酸値を下げるためには、生活習慣の見直しが必要です。尿酸値を上昇させるプリン体を多く含む食品やアルコールは控えます。さらに水分(水やお茶)を十分に摂取することで尿酸を体外へ排出させやすくすることも大切です。さらに適度な運動として、息がやや上がる程度の有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・水泳・自転車 等)を1日30分以上行うようにします。
何度も痛風発作がみられる、慢性腎臓病がある、無症状でも血清尿酸値が9.0mg/dL以上あるという場合は薬物療法も併せて行います。高尿酸血症の状態によって尿酸の産生を抑制する薬や尿酸の排泄を促進させる薬を使用します。
痛風発作が起きている時は上記の薬物療法を最初からは行わず、主に非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を使用し痛みを和らげ、尿酸値を下げる効果のある薬は症状が治まってから使用します。

